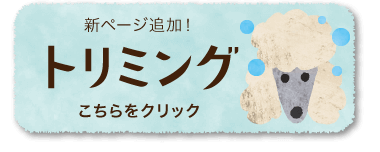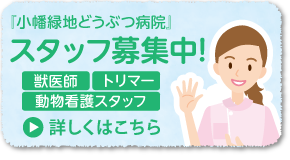突然、愛犬が足を引きずったり、歩き方がぎこちなくなったりするのを見つけたら、飼い主様としてはとても心配になりますね。その原因の一つに挙げられるのが「前十字靭帯断裂」です。犬の膝関節を安定させる重要な役割を果たす前十字靭帯は、断裂しやすい部位でもあります。
今回は犬の前十字靭帯断裂について、症状や原因、治療方法、予防のポイントなどを詳しく解説します。
■目次
1.前十字靭帯断裂とはどんな症状?
2.断裂が起こりやすい犬種と原因
3.診断方法
4.治療方法
5.手術後のケアとリハビリテーション
6.予防のために気をつけたいこと
7.まとめ:早期発見・早期治療の重要性
前十字靭帯断裂とはどんな症状?
前十字靭帯は大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)を結び、歩行時や運動時に膝の安定性を保つ重要な役割を果たします。この靭帯が断裂すると、以下のような症状が見られます。
・突然の跛行(歩き方の異変)
・足をかばう動作(片足を浮かせている、地面につけないなど)
・立ち上がりが困難
・膝関節の腫れや痛み
・座ったときに足を外側に投げ出す
症状の重さは軽度から重度までさまざまですが、放置すると関節の炎症が進行し、他の足にも負担がかかるため早期の診断・早期治療が必要です。特に部分断裂の場合、適切な治療を行わないと完全断裂に進行する可能性があります。
また、約50%の確率で反対側の足にも発症するリスクがあるため、継続的な観察が重要です。
断裂が起こりやすい犬種と原因
前十字靭帯断裂は、特定の犬種や条件下で起こりやすい病気です。
<大型犬の場合>
ラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、ハスキーなどの大型犬は体重が大きいため膝関節への負担が増加します。
<小型犬の場合>
トイプードルやチワワなどの小型犬は膝蓋骨脱臼を伴う場合、靭帯に負担がかかりやすくなります。特に若い小型犬の場合、遺伝的な要因による膝蓋骨内方脱臼(パテラ)が原因で発症することがあります。
<その他の原因>
・加齢による靭帯の自然な劣化
・肥満による過度な負荷
・急な踏ん張りや過度な運動
・がんや自己免疫性疾患
診断方法
前十字靭帯断裂の診断では、以下のような検査や手法が用いられます。
<整形外科学的検査>
・歩き方や座り方の観察
・脛骨前方引き出しテスト
・脛骨圧迫テスト
・膝関節の可動域検査
<画像診断>
・レントゲン検査:関節周囲の骨や軟骨の状態評価
・エコー検査:靭帯や半月板の損傷状態の確認
・必要に応じてMRIや関節鏡検査を実施
治療方法
治療方法は大きく分けて「手術療法」と「保存療法」の2つがあります。それぞれメリットやデメリットがあり、状態や飼い主様の希望によって治療方針を決定します。
【手術療法】
当院では、主にラテラルスーチャー法を採用しています。
<ラテラルスーチャー法>
人工靱帯を使用して膝を補強する手術方法で、小型犬から大型犬まで幅広く対応が可能です。ラテラルスーチャー法を用いた手術の手順は、以下の通りです。
①脛骨に特殊な穴をあけ、人工靱帯を通す
②骨との摩擦を軽減する工夫を施す
③体格や症状に応じて最適な素材(金属製ワイヤーなど)を選択
ラテラルスーチャー法のメリットとしては手術侵襲が比較的小さいため、体にかかる負担が少ないです。さらに、手術時間が短いため、麻酔のリスクを軽減できます。また、他の外科手術と比べて経済的な負担が比較的少ないことから、飼い主様にとっても取り入れやすい選択肢となっています。
今年より当院では以下の手術方法の導入も予定しております。
<TPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)>
TPLOは骨切りを行うことで脛骨の角度を調整し、膝関節への負担を根本的に軽減できる点が特徴です。この方法は、関節の安定性を高める効果が期待でき、長期的な予後が良好であることが多いとされています。
【保存療法】
症状が軽度な場合や高齢や持病により、手術が難しい場合に選択します。保存療法では、主に以下を実施します。
・消炎鎮痛剤による疼痛管理
・運動制限による負荷軽減
・リハビリテーション
手術後のケアとリハビリテーション
手術後の適切なケアとリハビリは、治療の成功に不可欠です。
【入院期間】
通常、術後の回復期間は3〜5日程度とされています。この期間は、適切な痛みの管理と傷口のケアが重要です。また、基本的な歩行が可能になるまで、愛犬をしっかりサポートしてあげることが大切です。
【退院後の経過観察】
術後の経過観察として、2週間後、1ヶ月半後、3ヶ月後に定期検査を行うことが推奨されます。検査では、インプラントの状態を確認することに加え、骨の癒合状況を評価し、運動機能の回復度合いを確認します。
【段階的なリハビリプログラム】
具体的なリハビリメニューは、術後の日数によって異なります。
<初期(術後1-2週間)>
・短時間の室内歩行
・軽いストレッチ
・マッサージによる筋肉のケア
【中期(術後2-6週間)】
・徐々に歩行時間を延長
・水中療法(可能な場合)
・関節可動域訓練
【後期(術後6週間以降)】
・通常の散歩に向けた調整
・筋力トレーニング
・バランス訓練
予防のために気をつけたいこと
前十字靭帯断裂を完全に防ぐことは難しいですが、以下のポイントに気をつけることでリスクを軽減できます。
<体重管理>
適切な食事量を調整し、栄養バランスを保つことが重要です。また、定期的に体重を測定し、増減を把握することで早めの対応が可能になります。特に肥満は関節や内臓に負担をかける原因となるため、予防を徹底することが大切です。
<運動量の調整>
急激な運動を避け、身体に無理のない範囲で運動させることが大切です。さらに、適度な運動量を維持することで、筋力や体力の低下を防ぎます。また、関節や骨に負担をかける過度なジャンプは避けるよう注意しましょう。
<環境整備>
ご自宅では床に滑り止めマットを敷くことで、関節や足腰への負担を軽減し、転倒のリスクを防ぎます。また、段差のある場所にはスロープを設置するなどして、移動がしやすいように工夫しましょう。さらに、無理なく運動できるスペースを確保し、犬がストレスなく身体を動かせる環境を提供しましょう。
<定期的な健康管理>
犬の健康を維持するためには、定期的な健康管理が欠かせません。定期的にエコー検査を実施することで、病気や異常を早期に発見し、適切な対応が可能となります。また、関節の健康をサポートするために、獣医師の指導のもとで関節サプリメントを活用するのも効果的です。
さらに、日頃から獣医師と相談しながら予防策を検討することで、犬が健康で快適な生活を送れるようサポートしましょう。
まとめ:早期発見・早期治療の重要性
前十字靭帯断裂は自然治癒が期待できない疾患です。そのため、症状が見られたら、早めに獣医師に相談することが重要です。また、早期治療を行うことで、より良い予後が期待できます。特に片側が前十字靭帯断裂となった場合は、反対側の予防と早期発見を心がけてください。
日頃から適切な予防策と定期的な健康チェックを行い、愛犬の健やかな生活をサポートしましょう。
愛知県名古屋市守山区
犬や猫、うさぎ、小鳥、ハムスター、フェレットなどの幅広い動物の診療を行う動物病院
『小幡緑地どうぶつ病院』
TEL : 052-778-9377