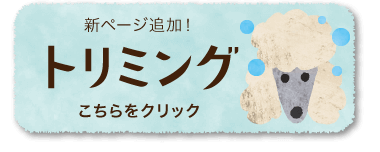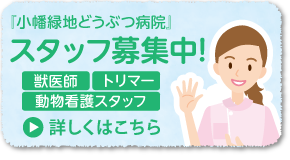「愛犬が目を細めている」「涙の量が明らかに増えた」と感じたことはありませんか?
このような目の異変に気づいたとき「もしかして失明してしまうのでは…」不安になる飼い主様も多いのではないでしょうか。
視覚は犬にとっても大切な感覚のひとつであり、異常が見られた場合は、できるだけ早く動物病院で診てもらうことが重要です。
特に「角膜潰瘍(かくまくかいよう)」は、進行が早く、放置してしまうと視力を失う恐れもある疾患です。
また、見た目では異変に気づきにくいことも多く、「もう少し様子を見ようかな」と迷われる飼い主様もいらっしゃいますが、角膜潰瘍は決して放置してはいけない病気です。
今回は犬の角膜潰瘍について、症状や原因、治療方法、予防法などを解説します。
■目次
1.角膜潰瘍ってどんな病気?
2.見逃してはいけない症状のサイン
3.原因
4.診断方法と治療方法
5.治療中の注意点と予防方法
6.まとめ
角膜潰瘍ってどんな病気?
角膜潰瘍とは、角膜と呼ばれる目の表面にある透明な膜に傷がつき、そこから細菌などが感染して、炎症を起こしたり角膜が白く濁ったりする病気です。角膜は非常に薄く繊細な組織で、小さな傷でも進行すると深刻な状態につながることがあります。
角膜潰瘍は傷の深さによって段階があり、浅いものであれば比較的軽い症状で済むこともあります。しかし、傷が深くなると角膜に穴があいてしまう「穿孔(せんこう)」という状態に進行することがあり、最悪の場合は失明してしまう恐れもあります。進行のスピードも速く、痛みを伴うため、犬にとっては大きなストレスとなります。
角膜潰瘍は、特に以下のような犬種によく見られます。
・シーズー
・チワワ
・パグ
・フレンチ・ブルドッグ
これらの犬種に共通するのは、鼻が短く、目が大きく出ている「短頭種」であることです。
目が外に出ている分、枝やホコリなどの外的刺激を受けやすく、角膜に傷がつきやすい傾向があります。
そのため、こうした犬種と暮らしている飼い主様は、日頃から目の様子をこまめにチェックし、少しでも異変があれば早めに受診することが大切です。
見逃してはいけない症状のサイン
角膜潰瘍を早期に発見するためには、日頃の観察が重要です。以下のような症状が見られた場合は、注意が必要です。
・目を頻繁にこすったり掻いたりする
・まばたきの回数が多い
・片目を開けようとしない
・目を細めている
・涙の量が明らかに増えている
・目やにが普段よりも多く出ている
・目が赤く充血している
・黒目のまわりが白っぽく濁って見える
さらに、以下のような変化が見られた場合、強い痛みを伴っていることがあります。
・顔を触られるのを嫌がる
・元気がなくなる
・食欲が低下する
特に、「黒目に白い斑点が見える」「角膜が盛り上がっているように見える」「目を異常に気にして激しくこする」といった様子があれば、角膜穿孔のリスクが高く、早急に動物病院を受診する必要があります。
また、動物病院に連れて行った際、興奮や緊張で症状が一時的に見えづらくなることもあります。そのため、異変に気づいたときの様子をスマートフォンなどで動画に記録しておきましょう。診察時に獣医師がその映像を確認することで、より正確な診断につながります。
原因
角膜潰瘍は、さまざまな原因によって引き起こされます。主な原因は以下のとおりです。
<外傷>
散歩中に草や枝で目を引っかいてしまったり、他の犬や猫との接触で引っかかれたり、砂やゴミなどの異物が入ることによって角膜が傷つくことがあります。
<まつ毛やまぶたの異常>
眼瞼内反症(まぶたが内側に巻き込む状態)や逆まつげにより、角膜に慢性的な刺激が加わると、潰瘍の原因になります。
<ドライアイ>
涙の分泌量が少なくなり、角膜が乾燥することで傷つきやすくなります。
<感染症>
細菌や真菌(カビ)、ウイルスなどに感染することで、角膜の傷が悪化して潰瘍が形成されることもあります。
<犬種特有のリスク>
前述したとおり、目が突出している短頭種は物理的に外部からの刺激を受けやすく、リスクが高いとされています。
診断方法と治療方法
角膜潰瘍が疑われる場合、まず「フルオレセイン染色」という検査を行います。これは、目に専用の染色液をつけて、傷の有無やどのくらい深いかを確認する検査です。傷がある部分だけが染まって見えるので、潰瘍の広がりや深さを調べることができます。
検査で角膜潰瘍と診断された場合、潰瘍の重症度に応じて以下のような治療を行います。
・軽度の場合:抗生剤の点眼薬で感染を防ぎながら、炎症を抑える治療を行います。
・中等度から重度の場合:点眼薬に加えて内服薬を併用したり、状態によっては外科的な処置を検討したりすることもあります。
なお、見た目がよくなってきても、角膜が完全に回復するまでには時間がかかることがあります。「治ったかな」と思っても、角膜が完全に再生していない場合、再発するリスクもあるため、最後まできちんと治療を続けることがとても大切です。
治療中は、獣医師の指示に従ってこまめに再診を受け、回復の様子を確認しながら治療方針を調整していきましょう。
なお、角膜潰瘍と診断されて治療を受けていてもなかなか良くならない場合には、よくあるセカンドオピニオンの例として「自発性角膜上皮欠損症(SCCEDs)」が疑われることがあります。これは通常の治療では治りにくいタイプの角膜潰瘍で、専門的な処置が必要になることもあります。そのため、症状の経過に不安があるときは、遠慮なく動物病院に相談することが大切です。
治療中の注意点と予防方法
治療中は、再発や悪化を防ぐために、以下のような点に注意して愛犬の目を守ってあげましょう。
・目をこすらせないようにする(エリザベスカラーの着用など)
・処方された点眼薬を指示通りに使用する
・清潔な環境を保ち、目に異物が入らないように注意する
また、角膜潰瘍を防ぐためには、日頃から以下のような対策を心がけると安心です。
・散歩時は草むらや枝の多い場所を避ける
・他の動物との接触はなるべく避ける
・目やにが出ている場合は、清潔なガーゼなどでやさしく取り除く
・毎日、愛犬の目の様子をチェックする習慣をつける
小さな異変にいち早く気づくことで、重症化を防ぐことができます。
まとめ
角膜潰瘍は、進行が早く、放っておくと視力に深刻な影響を及ぼす可能性のある目の病気です。
「目を細めている」「涙が多い」など、少しでもいつもと違う様子が見られたら、迷わず動物病院を受診しましょう。
適切な診断と早期に治療を行うことで、多くの場合、愛犬の視力を保つことが可能です。そして、何よりも大切なのは、飼い主様が日頃から目の状態をよく観察してあげることです。
当院では、犬の目に関する症状に対して、早期の診断と専門的な治療を行っております。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
愛知県名古屋市守山区
犬や猫、うさぎ、小鳥、ハムスター、フェレットなどの幅広い動物の診療を行う動物病院
『小幡緑地どうぶつ病院』
TEL : 052-778-9377