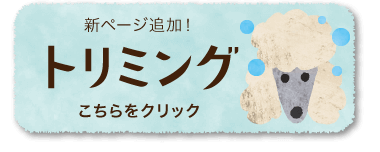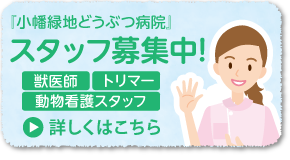「最近、愛犬の口がなんだか臭う」「歯が黄色っぽくなってきた気がする」そんなふうに感じたことはありませんか?こうした変化は、歯周病の初期サインであることが多いです。
実際に、3歳以上の犬の約80%が歯周病を抱えていると報告されており、決して珍しい病気ではありません。また、歯周病は口の中の問題だけでなく、全身の健康にも大きく影響を及ぼす可能性があるため、早期の発見と適切な対応が大切です。
今回は犬の歯周病について、症状や原因、治療法、予防のためのケアなどをご紹介します。
■目次
1.歯周病ってどんな病気?
2.こんな症状は要注意!歯周病のサイン
3.なぜ歯周病になるの?原因と進行のしくみ
4.歯周病の治療と当院での取り組み
5.予防が一番大切!おうちでできるデンタルケア
6.まとめ
歯周病ってどんな病気?
歯周病とは、「歯肉炎」や「歯周炎」など、歯ぐきに関連する病気の総称です。主な原因は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)や歯石で、これらが歯ぐきに炎症を引き起こすことで発症します。初期段階では「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなったりすることがあります。
この状態を放置してしまうと、歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)に細菌が入り込み、炎症が深部へと進行します。その結果、歯を支える骨や歯根膜が破壊される「歯周炎」に移行し、歯がぐらついたり、自然に抜けてしまったり、場合によっては抜歯が必要になることもあります。
さらに、歯周病菌や炎症によって発生する毒素が血流にのって全身を巡ると、心臓・腎臓・肝臓などの重要な臓器に悪影響を及ぼすリスクもあります。
こんな症状は要注意!歯周病のサイン
歯周病は初期には目立った症状が出にくく、見過ごされやすい病気です。以下のようなサインが見られたら、早めに動物病院を受診してください。
・口臭が強い(生臭い・アンモニア臭な)
・歯茎が赤く腫れている
・歯に茶色や黄色の歯石が付着している
・食べ方に変化がある(硬いものを避ける、片側で噛む、食べこぼしが増えるなど)
・よだれが増えている
・口元を触られるのを嫌がる
・顔まわりを気にするしぐさ(掻く、擦るなど)
さらに重症化すると、歯がぐらついたり、鼻血が出たり、顔の腫れが見られることもあります。これらはすでに歯周病が進行しているサインです。
なぜ歯周病になるの?原因と進行のしくみ
前述したとおり、歯周病の主な原因は歯に付着した歯垢(プラーク)です。この歯垢には多くの細菌が存在しており、それが歯ぐきに炎症を引き起こします。放っておくと、この歯垢が歯石となって固まり、さらに細菌が増殖しやすい環境がつくられます。こうして炎症が進行し、歯周病が悪化していくのです。
特に以下のような犬種は、歯周病が起こりやすいとされています。
・小型犬(チワワ、トイプードルなど)
・短頭種(パグ、シーズーなど)
これらの犬種は、歯の密集や顎の小ささなどの構造的な要因により、歯垢が溜まりやすく歯周病になりやすいとされています。
また、加齢により免疫力が低下すると歯周病のリスクが高まりますが、若い犬でも歯磨きの習慣がない場合や、体質的に歯石がつきやすい場合には発症することがあります。
また、ご家庭でのケアだけでは歯石の除去はできないため、定期的に動物病院でケアを受けることが大切です。
歯周病の治療と当院での取り組み
歯周病の治療方法は、進行度によって異なります。当院では、愛犬の状態に合わせて以下のような処置を行っています。
<軽度の場合>
歯ぐきにわずかな赤みや腫れが見られる程度であれば、歯磨きなど日常的な口腔ケアを見直すことで改善が期待できます。
当院では、歯磨きの方法やケア用品の選び方を丁寧にご案内し、ご自宅でのケアをしっかり続けていただけるようサポートしております。
<中等度の場合>
歯石の蓄積や歯周ポケットの炎症が進行している状態です。この場合は、麻酔下でのスケーリングや歯周ポケットの洗浄といった処置が必要になります。
<重度の場合>
歯を支える骨や組織が破壊されているため、麻酔下での抜歯が必要になることがあります。歯を失うことは心配かもしれませんが、痛みがなくなることで食欲や元気が戻り、生活の質が向上することもあります。
全身麻酔に不安を抱く飼い主様もいらっしゃいますが、当院では術前検査(血液検査・レントゲンなど)を徹底し、安心・安全な麻酔管理を行っております。
治療後にお口のケアを怠ってしまうと、歯周病が再発してしまうこともあります。そのため、当院では、治療後のアフターケアにも力を入れており、ご家庭でのケア方法や通院のタイミングについても丁寧にサポートしております。加えて、治療の精度を高めるための設備や、飼い主様のご不安に配慮したケア体制も整えています。
なお、当院では口腔内の状態をより詳しく把握するために、「歯科用レントゲン」を活用しています。歯ぐきの奥に隠れた炎症や歯の根の状態など、目に見えない部分まで丁寧に確認することで、より的確な診断と治療が可能です。
また、全身麻酔に不安がある飼い主様に向けては、「無麻酔スケーリング」にも対応しております。症例に応じてご提案しておりますので、まずはご相談ください。
予防が一番大切!おうちでできるデンタルケア
歯周病を防ぐためには、毎日のデンタルケアが欠かせません。ただし、いきなり歯ブラシで磨こうとすると愛犬が驚いてしまうこともあるため、以下のような手順で、少しずつ歯磨きに慣らしていきましょう。
①口の周りを触られることに慣れさせる
②歯ブラシが口元に触れることに慣れさせる
③歯ブラシが軽く歯に触れることに慣れさせる
④少しずつ動かしながら、歯を磨く感覚に慣れさせる
⑤磨く歯の本数や時間を徐々に増やしていく
これらのステップができたときには、しっかりと褒めてあげましょう。「いい子だね」「上手だね」などの声かけや、お気に入りのおやつをご褒美として与えることで、「歯みがき=嬉しいこと」と感じてもらえるようになります。
また、どうしても歯ブラシが苦手な子には、歯磨きシートやデンタルガム、飲み水に混ぜるタイプのケア用品もおすすめです。こうした製品を上手に取り入れながら、無理のない範囲で続けていくことが大切です。
さらに、歯周病の早期発見のためにも、動物病院での定期的なチェックを受けることをおすすめします。獣医師による適切なケアを取り入れることで、ご自宅のケアでは届かない部分の歯垢や歯石も除去することができます。
また、当院では「歯磨き教室」も実施しております。ご自宅でのケアが不安な飼い主様や、これから歯磨きを始めたいとお考えの方に向けて、実際に歯ブラシを使った練習や、お口の中を嫌がられずに触るコツなどをお伝えしています。「どう教えていいかわからない」とお困りの際は、ぜひお気軽にご参加ください。
子犬や子猫の歯磨きトレーニングのやり方や重要性、注意点についてより詳しく知りたい方はこちら
まとめ
歯周病は、予防と早期治療によって確実に対処できる病気です。口臭や歯の汚れといった初期のサインを見逃さず、気になった時点で動物病院に相談することが大切です。
また、毎日のデンタルケアに加えて、動物病院での定期的なチェックを取り入れることで、愛犬の健康を守り、快適な暮らしをサポートできます。
当院では、歯科診療についても安全で丁寧なケアを心がけております。気になる症状がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
愛知県名古屋市守山区
犬や猫、うさぎ、小鳥、ハムスター、フェレットなどの幅広い動物の診療を行う動物病院
『小幡緑地どうぶつ病院』
TEL : 052-778-9377